題 名
日 付
2003年09月30日
概 略
帝国憲法の持つ二面性とその危うさ
当時の世界の常識では、憲法はヨーロッパやアメリカのみの いわば白人社会によって作られるものであった。それが、遠く離れた東洋の一島国である「日本」で作られた。そのニュースは西洋の人々を驚愕させるものだったであろう。日本の存在自体 「東洋の野蛮な国」のように思われていただろうし、白人でもない人種にそれだけのものが作れるとは 想像も出来なかったはずだ。
日本は、あらゆる意味で 他の東洋の国々とは全く違った行動と運命をたどった。そのひとつの到達点が「大日本帝国憲法」であったことは、確かな事実である。ただし、その成立過程はどのようなものであったろうか?それこそが、日本にとってもっとも重要視されるべきものであったと、私は考えるのである。憲法は作れた。しかし、それは日本の国民自身による自発的な「憲法」ではなかった。そういった、一般人の意見を無視し あるいはそれを否定することから作られたられた「大日本帝国憲法」は 国民によって作られた多くの私擬憲法のなかのどんなものよりも保守的な内容であったのだ。
確かに、「大日本帝国憲法」では国民の自由や平等が謳われていた。しかし これらの項目が存在しなかったとしたら 「大日本帝国憲法」は憲法とは呼べないような代物となっていたろう。しかし、そういった国民の権利を盛り込むことが かえって「憲法」自体に矛盾を生じさせることになった。二面性と言ってもよいであろう。この憲法は、言ってみれば「欽定憲法」であり その中心をなすものは「万世一系の天皇」が「この日本を統治する」ことの宣言なのであって それを憲法という形に作り上げたに過ぎない。その反面、憲法という形式を持つ必要性から「自由や平等」を盛り込まなければならなかった。この二面性が その当人の都合の良いように解釈できる余地を生み 結果的に日本をあの悲惨な戦争へと向かわせたのだ。
当然、憲法作成の責任者であった伊藤博文もその危険性を認識していたのだろう。『憲法義解』によって 憲法の内容の解釈についての説明を述べているが、解釈する人は自分の都合でどのようにでも説明してしまうものだ。例えば、「大日本帝国憲法」よりもその内容が厳格に規定されている筈の「日本国憲法」。その第9条−『日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。全項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。』ですら曲解してイラクへの自衛隊派遣すら合法化してしまおうとする輩がいるのだ。大きな矛盾を孕んだまま出発してしまった「大日本帝国憲法」を その矛盾につけいって都合よく使ってしまう者がいても不思議ではない。
明治維新後の日本にとって最重要な事項のひとつに、不平等条約の解消があったことは言うまでも無い。そんな日本にとって、対外的に「日本はこんな風に近代的な憲法をつくりましたよ」というポーズを取ることが 重要な外交問題であった。岩倉使節団を送ったことや、鹿鳴館を作った事、それらは全て日本というこの国の優秀さ・特異性を外国に知らしめるための努力であった。そして、それまで白人社会にしか無かった憲法を作ることもその一環だった。しかし、その反面で「万世一系の天皇」が「この日本を統治する」という基本的な日本の形を変えたくはなかった。それが、二面性を孕んだ憲法を生み出したのだと考えるのである。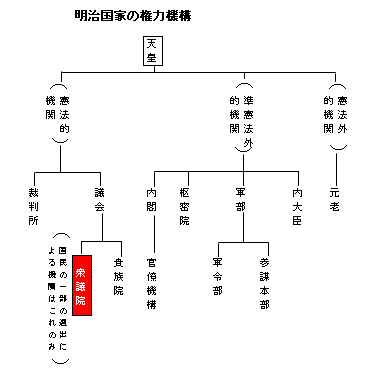
終戦の時、来日した連合国記者団長ラッセル・プラインズは、帝国憲法の二つの弱点として『統帥権が天皇に直属していること、予算の前年度踏襲制(明治憲法第七一条)にみられるように国庫支出にかんして議会の還元のせまいこと』(長谷川正安著 「日本の憲法」P23より引用)をあげている。なによりも注目すべきなのは、憲法という最高の法律に全くしばられないところに天皇が存在し、憲法上になんの定めもない御前会議が 日本の国内の最高機関だったことだ。天皇は全ての法律の範疇から抜け出たところに存在する最大でそして唯一の権力者だったことだ。絶対君主制といわれる所以である。
右に示した図は、色川大吉氏著の「日本の歴史21」のP490より引用させてもらったものである。国民による選挙によって選ばれるのは、図の赤色の部分(衆議院)のみであり、なおかつ憲法の範囲外である元老達の存在が、特色となっている。この図は 政府機構を模式的に示したものでとてもわかりやすかったので参考にしてください。